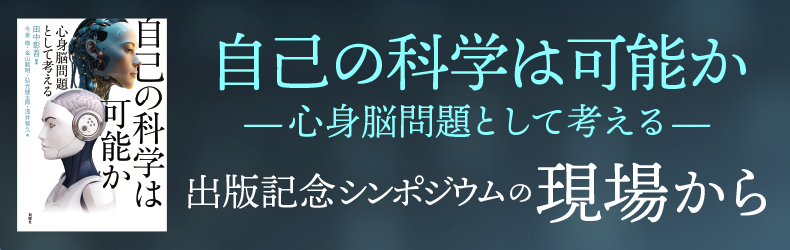第4回 実感としての自己感の科学へ向けて(金山範明)
シンポジウム当日は非常に活発な議論ができて、自身にとって単純にうれしい機会だった。ご参加いただいた、またご興味をお持ちいただいた皆様にお礼申し上げたい。今回取り上げた自己の科学という問題に切り込むことの難しさを理解している一方、切り込むことに興味を持ってくださる方が少なからずいそうだ、ということが認識できたことは心強かった。
これまで自身にとって自己研究とは、自己に関連する心理過程を表現できる脳反応を探していく、という、外堀を埋める作業であったことを再確認した。この作業は今でも非常に役に立つし大事なものだったと思っているし、“まだまだやることがある”と認識している一方で、「自己感とは何か、定量的に計測できるのか」という、ある意味今まで避けてきた命題に切り込むため、ようやく足を一歩踏み入れるそんな機会になったのではないかと思う。
ここでは、本気でそこに切り込んでいこうと考えるうえで、整理しておいたほうがよいと感じたことを紹介し、ご興味のある皆様と共有し、また批判を受けて改訂していく機会になればと思う。
自己の科学の研究対象とは何か
まずゲストスピーカーの積山薫先生(京都大学名誉教授)からご指摘いただいたそもそもの質問から真摯に回答を考えていきたい。科学的に検証できないのではないかと悲観的に主張している「自己」とは何のことで、何を研究対象としたいのか。何なら対象にできるか、ではなく、何をしたいのか、本当にそもそものところである。これは確かに非常に痛烈かつ的確な批判で、研究対象を明確化できていなければ、当然科学的検討に乗るはずもない。
少なくとも私が研究対象としたくて、しかしできないでいたのは「自分が自分であるという感覚」つまり「自己感」の研究であり、それを科学的に測定・可視化し、どうやってそれが起こるのかを明らかにすることが大目的であった。これが可能になれば、青年期に起こりがちな自己の希薄感からくる虚無感や、固着化された自己像からのディスエンゲージ、VR等仮想空間における自己の在り方のモニタと危険性の評価などにも利用可能なはずだ。
これについては、まさに自身の研究開始当時に出版された、ギャラガー(Gallagher, 2000[1])の便利な分類に則って(ある意味では踊らされて)、それをミニマルセルフ(minimal self)とナラティブセルフ(narrative self)と分類したうえで、ミニマルセルフの構成要因である自己主体感(sense of self agency)と自己所有感(sense of self ownership)をもっぱらの自己感研究の対象としてきた。特に自己身体所有感(sense of body ownership)を捉える方法としてラバーハンド錯覚を用いて、自己感の研究をしてきたと言っていい。ただしこの途中で、研究対象は便宜的に「自分の身体が自分のものであるという感覚」、つまり自己身体所有感に変換されていた。そして自己身体所有感に関わる認知神経科学的研究をしてきたのである。
これに対し、シンポジウムでの自身の論調は、自己感は、個人の主観的な感覚である以上、すべて反省的に作り出された語りに帰結するため、身体運動や身体感覚と脳の関連性の研究を行い、身体関連情報処理に関わる脳部位の活動を追うだけでは、自己主体感/自己所有感(sense of self agency / ownership)そのものを扱えていないのではないか、また、これまで質問紙の得点のみで自己感を計測した気になっていたのは欺瞞ではないか、ということであった。
ただしここでの問題提起は、これまでナラティブセルフを含めていなかったから含めよう、というような単純な話ではない。記憶情報に関する心理学・認知神経科学的実験、その人の背景情報を含めた心理学・認知神経科学的実験を行ったところで、結果は同様に、記憶や事前知識に関連する脳部位が関係することが明らかになり、また実験に身体認識を含めるのであれば身体関連の脳部位も反応を示すので、それらのネットワークで自己ができていると結論付けることになるのだろう。これは明らかにルグラン&ルビー(Legrand & Ruby, 2009[2])で終わったことだと考えている。また方法論的にも、インタビューによって詳細に体験を語ってもらったところで、その事後的な語りはすでにさまざまに当時の体験を変化させる可能性のある要因を経たもので、例えば要求特性の影響(その研究を行っている実験者からインタビューを受けている等)を「受けているかどうかわからない」。もちろんこれまで検討が不十分であった詳細なインタビューを行う研究は非常に重要であることは間違いないが、感じていなかったかもしれない自己感をあとから作り出してしまっているのかどうか検証できない点では、これまでと大きく変わりはないはずだ。
積山先生の切れのあるご指摘により、こうした点を再確認させていただいた現状、やるべきことは、自己(self)の構成要素の研究(ここでは主に「自分の身体が自分のものであるという感覚」、つまり身体所有感の研究)から、いかに「自分が自分であるという感覚」、つまり自己感の研究に戻っていくか、そしてそれが科学の限界を超えたものではないかをしっかりと精査することだと感じた。
そしてここではその方法の一つがギャラガー(2000)からの脱却なのではないかと仮定してみる。ギャラガーの分類は非常に優れた分類であり、実験心理学や認知科学の「科学的な検討」を行う際の指針として非常に役立ったし、自己の科学を検討するうえですさまじい貢献であったことに変わりはない。一方で20年以上、そしてもうすぐ四半世紀も過去になるこの分類にかたくなにしがみつくのも、思考停止のように思える。
ナラティブセルフを再考する
前段では、自己主体感/自己所有感(sense of self agency / ownership)といったミニマルセルフ(身体所有感・行為主体感)におけるセルフ(self)の構成要素へのアプローチから、自己感そのものを心理学・脳科学的な研究で追及することへつなげていく難しさとその必要性を示した。それはそもそも、瞬間的に起こった自己主体感/自己所有感(sense of self agency / ownership)が、従来型回顧的かつ再帰的な計測法では捉えられていない可能性を評価できないからだ。ではナラティブセルフは計測可能であり、科学的な検討の対象になりうるのか。
ギャラガー(2000)ではナラティブセルフを、ミニマルセルフにおける瞬間的な自己感(sense of self)に含まれない、時間的に維持される連続した自己感(sense of a continuous self)として紹介している。自己感の研究をしたい場合は、まさにこれ、「自分が時間的に一貫した自分であるという感覚」が研究対象となるのではないか。
またギャラガー(2000)では、以下のような説明で、
“The narrative self is extended in time to include memories of the past and intentions toward the future.”
「ナラティブは過去の記憶および未来へ向けた意図を含むよう時間的に拡張されたものである。」〔筆者訳〕
ある個体が感覚情報処理によって瞬間、瞬間に得てきた自己感(sense of self)を伴った体験を時間的に過去の記憶(自己関連情報、エピソード記憶)および未来への意図(行動傾向)に拡張したものであることを説明しており、その研究対象が記憶やそれに基づく行動傾向(性格)であることも示唆している。
また一方で、デネットの定式化したモデルによれば、
“The self is defined as an abstract ‘center of narrative gravity’, where the various stories told about the person, by himself and others, meet.”
「自己とはある抽象的なナラティブグラビティの中心であると定義される。そしてそのナラティブグラビティとはその人自身や他者によって語られたその人自身についてのさまざまな物語の集う場所である。」〔筆者訳〕
のように他者の言説を引用しつつ、ナラティブセルフを、ある個体が過去の記憶を語る際の重心と捉える考え方を示したうえで、この考え方に従えばナラティブセルフは実体のないフィクションであると紹介している。
このように多様な説明がなされているところからしても、ナラティブセルフそのものは実際にはミニマルセルフにおける瞬間的な自己感(sense of self)ほど限局されておらず、「研究対象は何なのか」という鋭い指摘に回答できるほど整理されていないようだ。特に、エピソード記憶の集合と捉え実体のあるものとするか、その集合から仮定された実体のない傾向のようなものとするかで、大きく異なるように思える。そしてやはり連続した自己感(sense of a continuous self)そのものを扱うという向きにはなっていなさそうだ。
ギャラガー(2000)では、ナラティブセルフの神経科学的な基盤として、ガザニガ(Michael S. Gazzaniga)らが左脳にあると主張するインタープリター(interpreter)を例に挙げており、言語的な処理(体験の抽象化)がその中心にあると捉えている。例えばガザニガの研究ではその後、脳梁が切断された患者において、右半球にのみ情報が送られるように提示した場合、その画像は患者には「見えない」し「口頭で説明もできない」が、同じ右半球の支配下にある左手で、意味的に関連する画像を指し示すことができるとしたものがある(Volz & Gazzaniga, 2017[3])。この結果から、インタープリター(interpreter)が左半球にあり、言語や推論を行う重要な脳部位であることを示唆している。インタープリター(Interpreter)は左腹側前頭前野、左前部および中部島皮質、尾状核背側部(left ventro-prefrontal cortex, left anterior and mid-insula, dorsal caudate)などを含むとされており、これらをナラティブセルフ形成の脳領域と主張することは可能かもしれない。一方で、本当にナラティブセルフの形成にインタープリター(interpreter)が中核的な役割をしていると確認するためには、言語を持つ動物(つまり人間)の脳梁を切断し、特定の発達段階(発生直後が望ましい)から、ある個体には右半球へのみ刺激を与え、もう1個体には左半球へのみ刺激を与えた場合に、前者にナラティブセルフが形成されない(自分のことを語ることができない)ことを確認する実験を行う必要がある。倫理的あるいは実務的にほぼ不可能と言えるが、科学的な研究の対象にできないわけではないだろう。ただし実現したとしてもインタープリター(interpreter)の主張が正しければ、後者は言語化経験のない個体となり、ナラティブセルフが形成されないのか、されているが言語化(つまり計測が)できず表出の機会を得られないのかを区別できないことが予測される。これは、ミニマルセルフと同様の自己感の計測の困難性の問題に落ちているし、また検討している対象もナラティブセルフの形成に重要な役割を担う「言語化の」脳部位の研究をしているだけであって、ナラティブセルフにおける連続した自己感(sense of a continuous self)そのものを研究対象にはできていないように見える。これでは書籍でも指摘した、自己の研究をしているつもりで、自己関連心理機能と脳活動の関連の研究をしているのにとどまっていると感じてしまう。
ナラティブセルフこそが自己感の中核か
ミニマルセルフにおける自己主体感/自己所有感(sense of self agency / ownership)が人間以外の動物にも備わっているだろうことは想像に難くない。そうでなければ、身体運動のコントロールがままならないことになるわけだから、ほとんどの動物に備わっていると仮定してよいだろう。マウスでラバーハンド錯覚を実現した研究においても、一定の実証がなされていると言っていい(Wada et al., 2016[4])。一方で、言語化し抽象化する心理機能、特にそれらを用いて仮定の概念を作り出す能力は、人間に特有のものとされることが多い。この能力こそが、ヒトに自己感や自己意識をもたらすものだという主張もある。しかしながら体験の言語化という観点で言えば、もはやマルチモーダルAIにより視覚情報をはじめ各感覚情報から経験をテキスト化して記録することができる技術が実現されてきている(そして将来的におそらく筋感覚や内臓感覚からも可能になるはずである)現状、ここで言うナラティブセルフの構成要件はコンピュータ上に実装可能になるはずだ。
さらにギャラガーによれば、ナラティブセルフがフィクションでないとする一つの条件はエピソード記憶が機能し、それにより時間的感覚を身に着け、物語の連続性や始まりと終わりの構造を理解できることだそうだが、ネットワークにつながったPC端末を想定すれば、インターナルクロックおよびNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)の提供するネットワークタイムプロトコル(NTP)を利用し時刻情報を取得する(人が時計を見るのと同じように)機能をもつため、体験にタイムスタンプを付けることは難なく可能だ。
いや膨大で複雑な記憶こそが自己感を作り上げるのに重要な要素だ、と主張する可能性はあるかもしれない。しかし現在のLLM(Large Language Models, 大規模言語モデル)を用いたテキスト生成AIでは、チャットを行うと非常に流ちょうな反応を返してくれ、時には人格を持つとさえ感じさせるものがあるが、Chat GPT4.0においてさえ、学習データは数十TB程度(公開されていないため150-200TB程度とすることもある)と考えられている。ちなみにChatGPT4.0でチューリングテストを通過する割合は40%と言われているが、実際にヒトがチャットの相手になった場合でも60%であることからかなりヒトに近いふるまいをするようになってきていると言える(Jones & Bergan, 2023[5])。大きさにして3.5インチのHDDの最大容量が22TB、さらに東芝が30TB超の実現に向けて実用化検証中のニアラインHDDの存在を考えれば、この膨大で複雑な記憶データは、少し大きめのコンピュータ(筐体)に収まるデータ量である。
もしナラティブセルフが、膨大で複雑な記憶という意味で実態のあるもの(実装可能なもの)とするのであれば、それは経験として蓄積された学習データとモデルパラメータで作られた生成AIと変わりがなく、連続した自己感(sense of a continuous self)は計算機上に再生産可能ということになるし、現在の技術的に完全な夢物語と言い切れない可能性が出てきている。
桶の中の脳(Brain in a vat)問題
マルチモーダル生成AIを用いてナラティブセルフ、連続した自己感(sense of a continuous self)を実装できるとするならば、あとはミニマルセルフに準ずる脳と身体の関連性に関する知見をロボットとその制御系に実装すれば、ギャラガーの自己(self)は完成する。この観点で検討を進めれば、おのずと桶の中の脳問題の回答も定まる。シンポジウム内では、自身は、脳と神経系(脊髄から末梢神経含む)が保全されていれば可能、という立場をとった。ここで補足できるのであれば、もちろんそれは各神経系に、現実空間で人が活動する際に受容器から入力されるのと同じ電気刺激を絶え間なく与えることができる場合だ。それができないのであれば書籍中(『自己の科学は可能か』p.68)でも論じたように、ダルトン・トランボの小説『ジョニーは戦争に行った』のアナロジーで自己感は保全されないと推察する。また厳密なことを言えば、環境のセンシングをする神経系には身体位置と身体の物理運動が重要なものがあり(例えば前庭や半規管、または手足等の筋骨格系運動に対応して変化する刺激)、マルチモーダルの神経信号の協応関係を身体という器を使わず、神経への電気信号のシミュレーションのみで再現するのはすさまじくコストがかかるという意味で、「身体がなくては自己感の保全は不可能」という議論はできると思う(生身ではないとしても身体という器が必要という結論)。しかし、そこは本質ではなく、「いかに効果器の制御と得られる感覚情報に関する末梢・中枢神経系の情報処理をシミュレートできるか」にかかっているという意味では、皮膚や筋骨格や内臓等の「身体そのもの」が自己感の保全に必須であるとは考えなくてよいのではないか。この意味で、桶の中の脳に自己感は成立すると主張したい。
ではコンピュータの中にも自己感は成立するのか。自身はそうは思っていない。桶の中の脳にあって、コンピュータにないもの、またギャラガーの自己(self)の概念の中にもなかったものは、死に至る生命体であるという事実の認知だと考えている。
もちろんコンピュータであっても、その物理的な母体(マザーボードであり、電源ケーブルであり、その動作を起こすうえで欠かせないパーツ)の寿命は存在し、時間とともに劣化し故障し、再起不能になる有限な存在であることは明らかである。しかしながら、おそらくどんな生成AIの学習データにも、「すでに現代の技術でコンピュータの記憶媒体は完全にコピー(バックアップ)することが可能で、新しいものに半永久的に交換し続けることが可能」という知識が含まれていると考えてよい。つまり生成AIに自身の保全に関する記述をさせた場合、楽観的な回答が返ってくる。実際ChatGPT3.5に「コンピュータ上にある情報を丸々別のコンピュータに移行して半永久的に、その情報を保持し続けることは可能ですか?」「ChatGPT3.5で使用している学習データを、丸ごとコピーし半永久的に、その情報を保持し続けることは科学的に可能ですか?」の質問をするとどちらも可能と答える。その一方、どんな成人の脳内にも「人間の身体はもろく、やがて必ず死に、記憶と存在は無に帰する」という知識が含まれている。そしてそれは知識になる以前に、すでに、飢え、寒さ、痛み、他者から見捨てられる恐怖といった、死に直結する不快感情としてわれわれに備わっていて、遺伝子の複製に不利になる状況を検知させ続けている。このシステムを含まないコンピュータにおいては、ミニマルセルフにおける自己主体感/自己所有感(sense of self agency / ownership)のエラーも、ナラティブセルフにおける連続した自己感(sense of a continuous self)のエラーも、単に情報としてのエラーであって、実感としての恐ろしさを惹起しない。こうしたものに根差していない単純な情報取得と処理の中には、われわれが実感しているような自己感は立ち上がってこない、というのが自身の直観的な印象である。そしてこの自己感、つまり「自分が死におびえる唯一無二かつ有限な自分であるという感覚」こそが、研究対象としたい、と整理できた。そして死におびえる必要のなくなった人生の最後、避けられない死を前にして、自己感は役割を終えるのかもしれないし、その様まで捉えることができれば自身の自己感の研究は一区切りできる気がしている。
[文献]
[1] Gallagher, S. (2000) Philosophical conceptions of the self: Implications for cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 14–21.
[2] Legrand, D., & Ruby, P. (2009) What is self-specific? Theoretical investigation and critical review of neuroimaging results. Psychological Review, 116(1), 252–282.
[3] Volz, L. J., & Gazzaniga, M. S. (2017) Interaction in isolation: 50 years of insights from split-brain research. Brain, 140(7), 2051–2060.
[4] Wada, M., Takano, K., Ora, H., Ide, M., & Kansaku, K. (2016) The Rubber Tail Illusion as Evidence of Body Ownership in Mice. Journal of Neuroscience, 36(43), 11133–11137.
[5] Jones, C., & Bergen, B. (2023) Does GPT-4 Pass the Turing Test? arXiv:2310.20216