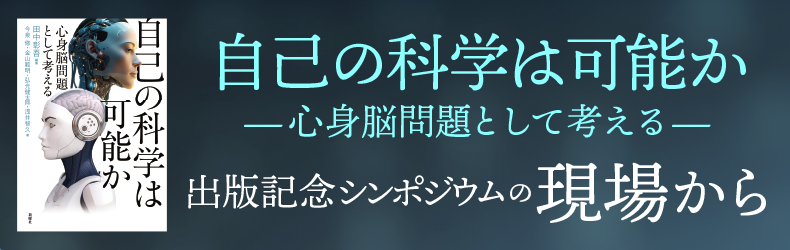第3回 自己であることと科学すること(田中彰吾)
シンポジウム当日は、多くの方々にご参加いただいただけでなく、会場でもZoom上でも数多くの真剣な質問とコメントをいただいた。ここに記して感謝しておきたい。今回は、当日の議論を振り返りながら、筆者自身が改めて考えたことを以下に書き留めておく。主な論点は「自己であること」と「科学すること」に関係している。
あらゆる経験に自己が随伴する
第一に確認しておきたいのは、当日も述べたことだが、「あらゆる経験に自己が随伴している」ということである。当日のコメントにも「心理学、認知科学、神経科学などの人の研究において、逆に自己ではないテーマというものというのがあるのだろうか?」という趣旨のものがあったが、もっともな疑問である。
友人と話をする、道を歩く、本を読む、自動車を運転する等、およそどのような経験であったとしても、それは「私の経験」という暗黙の感じをつねにともなっている。2000年ごろに、認知科学と現象学の接点で新たに登場した「ミニマル・セルフ」という概念は、この「あらゆる経験に随伴する自己という感じ」を捉えた点でラディカルな(radical=根源的な)ものだった。
この点を踏まえれば、心理学や認知科学や神経科学はもちろんのこと、当日のコメントで挙がっていた現象学、エスノメソドロジー、ナラティブ・アプローチなどもすべて「自己」に関連する研究を行っていることになる。何らかの「経験」がそこに生じており、その経験の中から「主体」が生成してくる過程を解明する研究なのであれば、それらは広い意味での自己研究であると言える。
反省は経験を変える
だが、そうであればこそ「自己を科学する」ことは容易ではない。重要な一例として、当日のディスカッションでも話題になった「反省」の問題を考えてみよう。
質問紙を使用してラバーハンド錯覚のような経験を振り返って回答してもらうとき、「錯覚が生じた時点でのありのままの経験内容」を回答内容が表現していると考えるのは難しい。それは、経験を振り返るという「反省」の作用が介入することによって、経験それ自体の質を微妙に変えてしまうからである。
食べ物の味に喩えるとわかりやすいだろう。あなたは誰かと一皿のパスタをシェアして食べた。そのとき目の前で友人が放った「おいしいね!」という一語をきっかけに、あなたは自身の味覚経験を反省し始める。あなたは「おいしい」と自ら声を上げるほどおいしいとは感じていなかったが、「おいしくない」と感じていたわけでもない。どちらかというと「おいしい」と感じていたものの、それがどの程度の、あるいはどのような質の「おいしさ」だったのか自分で確かめようとしても、経験そのものはもはや過ぎ去ってしまっている。後から反省することでそれなりに経験を再構成できるようではあるが、それは当初生じた「経験それ自体」とはやはり異なっている。
ミニマル・セルフとともに生じている経験は、このように、つねにすでに「生きられたもの」である。反省を通じて迫ろうとしても、過ぎ去った経験それ自体にはうまく迫れない。言葉にできたと思っても、その細部において、進行中の経験とは微妙だが決定的な差異が生じているように感じられる。自己に迫る最初の入り口である「経験」が、暗黙のうちに過ぎ去っており、しかも同じ経験が一回しか生じないとするなら、反省し、言語化することで経験の内実を解明することは最初から大きな困難をはらんでいる。
それゆえ、再現性のある科学的研究にしようとするなら、経験に対する網の掛け方を粗くするしかない。つまり、厳密には同じ経験とは言えないが、一定の範囲で「同じ」とみなすことができる経験を繰り返し、そこに含まれる質・条件・構造を明らかにするしかない。
ラバーハンド錯覚では、錯覚生起中にマネキンの手が自分の手であるかのような感じ(身体所有感)が生じるが、ここに一定の「粗い網」を掛けることで、身体所有感として生じる「自己」に迫っていくことになる。多くの研究者が気づいている通り、従来のような質問紙では網の掛け方が粗すぎる。錯覚経験中の感じ方を詳細に言語化してもらうマイクロ現象学の方法と、経験中の脳波やNIRS(Near-infrared spectroscopy; 近赤外線分光法)の測定データとを照合するような研究方法のほうが望ましいだろう。筆者自身も、進行中のプロジェクトでは、フルボディ錯覚を題材にしてこの種の研究に取り組んでいる。
トップダウンの要因
つねにすでに反省以前に生きられている経験に迫ることは、別の面から見ても困難をはらんでいる。それは、経験している主体自身の中に、経験に対する予測的な構えが内在していることに由来する。「脳は予測の器官である」と言われるようになって久しいが、ひとは環境との相互作用を一定のパターンで繰り返すことで、外部世界についてのモデルや出来事についての予期を生体内部に持ち合わせている。
あらゆる経験は一回限りのものかもしれないが、一回限りのものの中にも共通の要因は多々含まれている。例えば、コーヒーの味は原産地が違えばずいぶん変化するが、そうは言っても総じてそれらは「コーヒー」の味であって、緑茶やコーラの味ではない。その一方で、「コーヒーをどうぞ」といって差し出された緑茶を飲むのと、「コーヒーをどうぞ」といって差し出されたコーヒーを飲むのとでは、経験の内容は確実に変わる。経験は、主体の内部で事前に形成されている予測の枠組みによって、トップダウンの影響を受けるのである。
この種の予測の枠組みは、個人的経験に由来するものもあれば、言語的・社会的・文化的な学習に基づいて構成されるものもある。例えば、スキーの経験を豊富に持ち合わせている人であれば、スキー場に行って雪を最初に見たときの印象から雪の質感をある程度予見することができるだろう。あるいは、日本語話者であれば「青リンゴ」という言葉を聞いて「海の色のようなリンゴ」を思い浮かべる人はいないだろう。知覚を通じて経験が始まる前の時点で、「どのような経験が生じるべきか」ということについて、主体の側が事前に投射(プロジェクション)を暗黙に行っているのである。
予測と投射は言語的なものでもあるので、当然のことながら、他者との言語的相互作用によっても影響を受ける。とくに、どのような経験が生じるか予測がつかない状況では、事前に他者から得た言語的な情報によって、経験の質が左右される。ラバーハンド錯覚に対する批判として、実験のセッティングや実験中の教示によって(つまり要求特性によって)錯覚が引き起こされているのではないかとする主張があるし、シンポジウム当日もこの点に議論が及んだ。
要求特性に錯覚を還元する主張が全面的に正しいとは筆者は考えない。というのも、経験は、実際の知覚から始まるボトムアップな側面がなければ完了しないため、程度の大小はあれ予測からの誤差が必ず含まれるからである(この誤差こそ「意識」の発生根拠である)。とはいえ、実験参加者が事前に保持している予測的な構えによって錯覚経験に影響が生じる面はもちろんある。実験中に生じる経験について、参加者側で踏み込んだ予測ができるような状況は、少なくとも避けるべきである。
何を研究すればいいのか?
以上のような制約を考えると、自己を――ここではナラティブ・セルフまで十分に話が及ばないのでそれは別の機会に譲るが――科学的に検討できる範囲は、おのずと狭まってくる。考慮すべき条件は二つである。
(1)事前に予見できる範囲が制約されており、経験の内容を主体が見通せないこと。
(2)一定の範囲で繰り返すことができ、緩やかな意味で「同じ」とみなすことができる経験を題材にすること。
これらの条件を満たすものはそう多くないが、一例として、ある環境下で新しい経験を学習することで自己が変容していく過程を挙げることができる。古典的な例で言うと、ジョージ・M・ストラットンが逆さメガネに適応する過程についての記述を残しているが、彼の研究には自己研究として参考になるものが多く含まれている。現代的には、VR環境下で特定のアバターに適応していく過程や、脳卒中後のリハビリテーションを通じて自己身体に適応していく過程などが候補として考えられる。
学習過程の一人称的記述は、記述が厚く豊かなものであればあるほど、どこまでがトップダウンの予測的構えであり、どこからがボトムアップの知覚経験であるのか、示唆に富む洞察を多く含むものである。質問紙や生理指標から得たデータの「平均」を見る前に、トップダウン要因とボトムアップ要因について研究者自身がある「感度」を持っていることが重要である。逆にこの種の「感度」があれば、平均を求める前にそもそも何を測るべきか、という着眼において、凡庸な過ちを避けられるように思う。
そしてここには、「科学」をどう考えるかという論点も含まれている。一般には、一定の公共性と再現性のある知識を科学と呼ぶが(科学の公理系をめぐる議論は別の機会に譲ることにしてここでは踏み込まない)、Aさん・Bさん・Cさんという個別具体的な「自己」だけを問う限りそこに再現性はなく、科学にはならない。個別の「自己」を対象として取り上げつつも、それが個別の自己として成立する際に備えている条件、また、他のどのような自己にも同等に該当する形式を取り出すときができたときに、はじめてそれは「自己の科学」と呼びうる知識になる。
特定の環境下で新たな経験を学習する過程は、それが一例の記述に過ぎない場合であっても、「特定の条件が一定のしかたで変化すれば、別の人物にも当てはまる」と予測できる知見を豊富に含んでいる。つまり、記述を追うことで、ある時点での自己の「状態」を特定し、ある状態から別の状態への「遷移」の分岐パターンを特定することができる、ということである。このような「状態遷移モデル」を構築することができるのであれば、実験的手法であっても質的研究であっても、「自己の科学」は十分に成立しうる。逆に、「状態」から「状態」への遷移、遷移の時間的な分岐を扱わない研究は、重大な点において「自己」を取り逃すことになると思われる。
当日の質問に答える
最後になってしまったが、当日筆者に宛てられた質問が2件あったので個別に応答しておきたい。
Q 反省と身体性の関係
反省的意識が創発するうえで身体性は不要ではないか? 言語があれば反省が生じるには十分ではないか?
発生的に考える限り、答えは否であろう。ChatGPTのような大規模言語モデルは、人間ときわめてスムーズな言語的相互作用を展開することができるが、人間と言語のやり取りができるということと、反省ができるということは同じではない。反省とはそもそも経験をある時点で過去に遡って振り返るということである(と同時に、これから生じそうな経験を前方に向かって展望することである)。大規模言語モデルは、反省がそこから生じてくるような「経験」をそもそもしていると言えるだろうか。
反省は、「私が私の経験を振り返る」という「I-Me」の再帰的構造を内蔵している。人間の身体は、触覚や聴覚のモダリティにおいて「I-Me」の再帰的構造を内蔵している。私は私の身体に触れることができ、私は私の声を聴くことができる。発生的に見る限り、これは、言語を使った反省が生じてくるうえでの必要条件である。言語の獲得はむしろ、反省が成熟するうえでの十分条件であろう(例えば、ゾウやイカも反省的意識を持っている可能性があるが、言語を用いた成熟した反省はできないだろう)。
身体性を備えたロボットに大規模言語モデルを実装する研究が始まっているが、その種の研究には個人的にも期待している。身体性と言語を有するロボットははたして反省的な自己意識を持つことができるのだろうか? 筆者自身も考察してみたい問いである。
Q ナラティブ・セルフが解消する瞬間について
亡くなる前に人生の走馬灯を見るという話があるが、これは、それまでの長い人生を一瞬に収斂した瞬間、もしくはミニマル・セルフとナラティブ・セルフが完全一致するような瞬間なのだろうか?
端的に「わからない」としか答えようがないところもあるが、それでは面白くないので、多少の推論をしてみよう。死ぬ瞬間に限らず、ひとの人生経験の中には、情動が強く揺り動かされるとともに、それまでの過去を一瞬のうちにいわば「生き直す」ような出来事が生じることがある。例えば、「一目惚れ」のような経験がそうだろう。ある相手に強烈に惹かれる経験が生じることで、いままでの出会いの経験が相対化されて価値のなかったことのように感じられ、場合によっては「自分はこの人に出会うために生まれてきたのだ」とさえ感じられる。滅多に生じない経験だが、まったく生じないわけでもない。
問題は、この種の一目惚れが勘違いかどうかということではなく、それだけ深く情動が揺り動かされる経験では、過去が一気に生き直されるような独特の時間経験が生じる点にある。例えば、交通事故に遭って身体が宙を舞い「もうだめだ」と思うような瞬間も同様のことが生じているかもしれない。「自分はもう死んでしまう」と本気で感じる瞬間には、過去の数々の経験が一瞬のうちに相対化されて、「すべてがこの瞬間に向かって進んできたのだ」と思われるようなライフレビューの経験が生じる可能性はあるだろう。
ここには、「自己」を成立させる条件としての「時間性」をめぐって、考察すべき重大な論点が潜んでいるように思う。