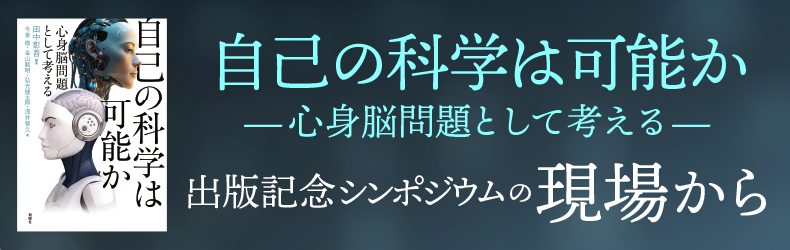第2回 自己という檻の中(弘光健太郎)
第2回である今回は、シンポジウムの中でいただいた質問や意見を踏まえて一人称視点という概念から自己を概観した上で今後の展望に話を展開していく。
本シンポジウムでは、自己の科学の限界点を提起し、同時にそれをどう乗り越えていくかが熱く議論された。登壇者がこのような問題に熱を持っているのはそうであるとして、印象的だったのは、聴衆がこれを受け入れ、かつ、現地でもオンラインチャット上でも話題提供の内容に閉じない議論が発生したことである。これは、少なからず自己についての研究を実践してきた人の、内に秘めていたもどかしさが露呈した結果だろうと思われる(書籍では特に第Ⅱ部でその「もどかしさ」が議論されている)。自己を科学する上で、心・身体・脳の関係性はどうなっているのか、従来研究のようにその中の二者関係を扱うだけで十分なのか、そもそもそれらが相関するという前提は疑われなくてよいのか。そして、自己の測定問題と科学という公理系の限界にまで話題が及んだわけである。このような、自己研究の根本を問い直す議論の素地を固める上でも、今回はシンポジウムの中で表には出てこなかったが、それでも自己というものの私秘性を考え、科学という公理系で扱えるかを考える上で重要な概念と思われる「一人称視点」から話を広げたいと思う。実際、チャット上でもシンポジウムの展開に並行して一人称視点が自己においてどのように関わっているのか、VR空間内での自己成立の契機として一人称視点が重要ではないかという言及が見られたので。
自己性の契機としての一人称視点
私たちは何かを経験するとき、どのような経験のしかたをするだろうか。経験というと漠然としているが、仕事に電車で行く、スプーンでカレーを食べる、亡くなった祖母の顔を思い出すなど、どのようなものでも構わない。このような経験はいずれも私の経験であり、そう感じられる(余談ながら、これこそがショーン・ギャラガーが言及した所有感――Sense of Ownership――である)。その経験のしかたに焦点を当てたとき、共通するのが一人称視点を介している点である。つまり、私は私自身の視点(一人称視点)を基点として世界を経験していると考えるのである。一見、私たちの経験は物理的には視点というよりむしろ、身体だけを介しているように見える。しかし、過去や未来に思いを馳せるとき、必ずしも身体は必要とはならない。もちろん言語を使っている場合も含めて、その経験は他ならぬ一人称視点を介しているはずである。自分を含んで世界を見るような三人称視点の場合もあるが、俯瞰している時点で一人称視点に内包されると考えてもよいだろう。
さて、自己を考える上で一人称視点が持つ重要性は、身体に根ざすとともに脳内にその表現があると考えられている点に加え、一人称視点を介した経験がその人自身の中に閉じている点にある(自己の私秘性に通じる)。このような一人称視点の意味を考える上で、シンポジウムのテーマともなった心身脳の3体問題とも絡んで、身体と脳との関係に焦点を当ててみる。関連して、当日「身体と脳を分ける妥当性はあるのか」という質問があったが、これはもっともな質問で、たしかに脳は身体の一部である。しかし一方で心との相関を考えたときに、焦点を単一の身体に当てるより脳との相関に当てる方が筋がよいと考えられてきたからだと推測する。そしてこの推測は、ブローカに端を発する、これまでに蓄積されてきた脳損傷者における心の機能障害の研究に基づいている。つまり、物理的な実体としての心の相方を探したときに、それをどのようなレベル、あるいは単位に求めるかという問題である。
話を身体と脳の関係性に戻すと、たとえば身体の感覚や運動が脳に表現されていることは有名だが、このような表現は脳だけでは成立しないはずである。つまり表現するためのソースとしての身体が必要となる。そして、身体が環境の中で動き回ることで、脳の状態を変えていく。同時に、脳が身体の状態を調整したり、運動のために制御したりもする。このような身体と脳の相互作用ないしループ構造がまず前提にあるだろう。その上で、個としての、脳を含む身体は環境からさまざまな入力を受ける。目で見るものであったり、耳で聞くものであったり、足で踏みしめるものであったりと、感覚器官を通して情報が入る。このとき、このような環境からの入力に対して個体は自身を維持しようと努めると同時に、そのために自身が持つ入力の事前情報との差分を小さくする形で活動する。このような環境と個体との区別こそがバイオロジカルな自己性と呼べるものなのかもしれない。環境から自己を切り出すという表現もできるだろう。その切り出しにおける個体と環境との媒介点としての機能を説明することが、一人称視点という構成概念を用いる意味である。もちろんそこに主観的な経験が生じる必然性はない。しかし、私たちは世界におけるあらゆる経験の媒介点としての一人称視点を介して(それが視覚入力でも聴覚入力でも触覚入力でも)主観的に一つにまとめ上げられた生々しい体験をする。そして、一人称視点が身体上でも特に頭部に根ざすという知見が蓄積されてきたことも興味深く、環境との接点の持ち方が、ヒトが視覚優位な生物という点で、視覚機能に大きく依存しているからなのかもしれない。
自己という檻の中
上で書いた話をもとに、シンポジウムでの議論やチャット上のコメントを受けてこの記事で言及したかったのは、一人称視点のような私たちの経験の中心点なるものが実体として存在するから重要だ、ということではない。むしろ、私たちが環境の中で身体を伴って運動することで、一人称視点を介して自己性を帯びるのだとすれば、それは個体の中で閉じた現象であり、何者にもアクセスされ得ないという点である。環境という物理空間に生きている(と思われる)私たちが、身体を伴って運動することによって世界を内在させ主観的な経験を生きるのだとすれば、内在された瞬間に最早そこには(物理的な)外の世界は存在しないことになる。このような自己における自身以外がアクセス不可能であるという特徴こそが、科学という公理系から自己を理解する障壁になっている可能性は、シンポジウムの中でも大きなテーマとして議論された。不良設定問題として諦める方向性もあるだろうし、あるいは同じAgentとしての他者との関係性から理解する方向性もあるだろう。さらには現代科学と一線を画す別の公理系に答えを求めるのも大きな一つの方向性である。今回の記事でそこに答えを出すことはできないとしても、最後に一つの議論として、自己という主観経験の意味を考えたい。
ここまで、一人称視点という概念を用いて、身体や脳が自己とどう関わるかを簡単ながら見てきた。もちろん一人称視点は構成概念であって実体はないし(心もそのはずだが)、安易に構成概念で構成概念を語るべきではない、というのは自戒を込めて書き記したい。ただ実体はなくとも、あらゆる経験が一つにまとめ上げられ、個体の中に閉じているという、内在性とでも呼ぶべき一人称視点の特徴こそが、生々しい私たちの経験を生み出しているのだと思われる。一方で、私たちの主観が外から目に見えて観察可能な代物だとしたら、現代科学の俎上にうまく載るものではあろうが、おそらく主観的な生々しさは必要ないので(外から見てわかるほど明確なので)消え去っていたのではないだろうか。主観経験が錯覚的なものであるとする立場もあるが、そう感じると錯覚してしまうことこそが主観的な経験なのであろう。
本記事では「自己という檻の中」というタイトルをつけたが、これは決してネガティブな意味だけを含むものではない。限りなく現代科学という公理系で扱えないという点で、自己は内に閉じており、外からはアクセスできない檻の中にいるようだという含意がネガティブな方である。しかし、外からアクセスできないことこそが、個体として生存していく上で意味があった可能性はないだろうか、というポジティブな含意もある。他者とのインタラクションを想像したときに、たとえば顔色にすべてが出てしまう人が稀にいるが、それが最大限に顕著になった場合には(内に閉じた経験が存在しない状況)、社会の中で生きていけないことは想像に難くないだろう。もしそうであるとするなら、自己を理解する上で、客観的な表現を用いることは適さないし、ばらつきのあるその人自身の主観をより緻密に検討する方向性の方がよいだろう。書籍内でも議論した平均主義に見られるような問題の背景には、均一化された反応の想定があるわけだが(行動にしろ脳にしろ)、こと自己を扱うときには翻って単一例を詳細に検討するということも現代科学という枠組みで闘うのならば一つの方法ではないだろうか、と考えさせられた。
シンポジウムにおける心身脳問題という議論の核心から最後は少し逸れた感はあるが、当日のコメントも踏まえつつ、筆者なりにこれまでの研究から脱却することの可能性について考えてみた。次回以降もシンポジウムの現場で生じた議論に基づき、そしてそれを発展させて、自己の科学について議論が展開されていくことと思うので、楽しみにお待ちいただきたい。